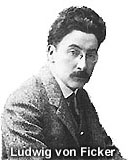|
訳者序
「そして、そこに」、とトーマス・マンは『魔の山』最終章で書いている。
「……そして、そこにあのオーストリア・ハンガリー皇太子夫妻の射殺事件が起った。これは七年間の眠りに陥ちている一ドイツ人以外には、他のすべての人々にとって、やがて襲いかかってくる嵐の前触れであったし、見る眼のある人には、これは決定的な事態と映じたのであったが、この慧眼な人々のうちにセテムブリー二氏を数え入れていいことはいうまでもない。ハンス・カストルプはセテムブリー二氏が私人として人間として、こういう凶行に対して慄然とするのを見たが、同時に、その行為が氏の憎悪する反動の牙城ウィーンに対する民族の自由解放を求める動向であることを考えて、氏が胸を高鳴らせるのを見もした。しかし、その行為はモスクワの教唆による結果とも考えられたので、セテムブリーニはまた憂欝そうになった。にもかかわらず、三週間後にオーストリアがセルビアに最後通牒を送ったとき、彼はそれを人類の汚辱、恐るべき犯罪だと断言するのに躊躇しなかった。その事態の結果に関しては、慧眼なる彼はそれを予測することができたし、かつそれは彼が胸を弾ませつつ待望したところであった[……]」(新潮世界文学34トーマス・マン『魔の山』、七七〇頁。高橋義孝訳)
一九一四年七月二八日、オーストリアはセルビアに対して、さらに八月六日にはロシアに対して宣戦を布告した。その間、八月一日にはドイツ帝国のロシアに対する、その二四時間後にはフランスに対する宣戦布告がなされ、八月四日には英独間の国交も断絶された。全ヨーロッパは文字通り、六月二八日のあのボスニアの都サライェヴォでの事件を機に、帝国主義列強の「屠殺場」と化していったのである。
トラークルは一愛国者として当然のごとく戦役に志願し、インスブルックを発った。それは八月二四日の夜、「月が煌々と冴え渡った静かな夜」だった。
友人にして父親的な存在でもあった文芸誌『ブレンナー』の主幹ルートヴィヒ・フォン・フィッカーは戦線に赴くトラークルを駅頭に見送った。かれの帽子の赤いカーネーションが「まるで幽霊のように、別れの挨拶を交す度に」揺れていた。家畜用貨車に乗り込む直前、別れに際して、トラークルは黙ったまま友人に一枚の紙片を手渡した。そこには――
「死にも似た存在の瞬間における感情、全て人は愛に価する。目覚めたまま、お前はこの世の辛酸を味わう。そこにお前の癒されぬ罪の全てがある。お前の詩は不完全な罪の償い。」
と書かれていた。問いかけるような眼差で、その時フィッカーが見上げると、トラークルは、「勿論、いかなる詩も罪の償いにはなり得ませんが」と言い添えた、という。その後のトラークルについては知りようがない。だが、少くとも八月二六日にはトラークルはまだウィーンにいたことは確かである。その後更に何日かして、消印のない野戦郵便用葉書がフィッカーの元に届いた。
「今日、ガリシア地方に向います。本来の目的地にはわずか一時間足らずの滞在にすぎません。これまでの旅は快適でした。われわれはおそらく、さらに三日間を車中で過ぎなければならないでしょう。」
トラークルがこの戦争に対して肯定的な意見を持ち、志願兵として戦地に赴いたとしても、かれがこの戦争の本質的な事柄をどの程度洞察していたか、という問題になると、極めて否定的な答えしかおそらく出て来ないだろう。かれの観念において戦争はその歴史的意味を欠落し、人間の普遍的、黙示録的な悲惨として捉えられていったこともまた確かである。その意味で、かれもまた表現主義作家のひとりとして、ルカーチが次のように指摘しているところの表現主義の世界観的本質性向から免れてはいなかった。
「世界観的にみてなによりもまず重要なのは、表現主義者たちが〈現象〉をつきぬけて〈本質〉にむかうそのやりかたである。ピントゥスが十年間にわたる表現主義の理論と実践を総括して答えていることを見てみよう。いわく、『周囲の現実を解体して非現実に変えること……がはじめられたのである。』しかしながらこれは、たんに問題の主観的・観念的な解決であるばかりでなく、というのはつまり、現実そのものの変化(現実の革命)から現実についての観念の変化へと問題をずらしてしまうことであるばかりでなく、同時にまた、現実からの思想的逃避でもある。」(『ルカーチフロッポーゼーガース表現主義論争』池田浩士編訳盛田書店刊。傍点引用者)
トラークルがこの戦争にもし何ごとかを求めていたとするなら、それはおそらく、オットー・バージルの言うように、「かれ自身の諸々の困難の終局」そのものにほかならなかったのかも知れない。つまり、かれにとって戦争は、その破壊的な力でかれ自身の生も含めて、いっさいの地上の否定的なものを終局させるという、この否定の否定という点にのみ意味があった、と言いうる。
八月二六日から三〇日にかけての五日間、オーストリア軍はガリシア地方で初めてロシア軍との間に砲火を交える。だが、圧倒的な敵の戦力と巧妙な戦術の前に、第二軍及び第三軍は潰滅的な敗北を喫して、レンベルク近郊グローデクまで後退する。九月一日、レンベルクが敵の手に落ちると、時の参謀総長コンコード・フォン・ベッツェンドルフは直ちに都市奪回作戦の命令を下した。だが、このかれのいわば盲目的とも言える作戦命令によって、オーストリア軍は再度の敗北と、全面撤退を余儀なくされる。そして九月一一日、東ガリシア全域がロシア軍の手中に下る。
「これらの戦士たちは、すでに一日中続いた戦闘に止めを刺し、二日前に敵に占領されたあの丘の陣地と、その向うに燃えているいくつかの村落を奪還するために出動したのであった。そしてこれは志願兵ばかりの連隊で、青年、大部分は学生であって、戦場へ来てからまだいくらも経っていなかった。彼らは夜中に出動命令を受け、朝方まで汽車で運ばれ、昼過ぎまで雨の泥淳の道――それはとても道とはいえなかった――を行軍した。街道はすべて遮断されていたので、彼らは畑地と沼沢とを七時間も、雨で重くなった外套を着て、突撃装備のまま、強行軍してきたのであった[……]
そうして彼らはやっと今ここに到着したのである。若い肉体はあらゆる困難を乗りきった。興奮し、すでに疲労困憊の極に達してはいたが、しかもなお最後のエネルギーを振りしぽって緊張に耐えている肉体は、睡らず食わずの強行軍をものともしなかった。彼らの濡れた、泥のはねかかった、軍帽の顎紐をきりりと締めた顔は、灰色の覆いをした鉄兜がずれている下に燃えるように紅潮している。彼らの顔は緊張のために、また泥濘の森を進撃中に蒙った味方の損害を見ないために、赤く燃えていた。彼らの進撃を知った敵は、榴散弾と大口径の榴弾の集中砲火を浴びせて、その進出を阻止しようとした。その砲火はすでに森の中を進撃しているときから隊列中に撃ちこまれて炸裂し、咆哮し、跳ね上がり、火を吹き、広い鋤き返された畑地へ叩きつけられた。」(トーマス・マン、前掲書、七七四頁)
そして、小説『魔の山』は、この戦争の濠々と立ち登る硝煙の彼方に向って、ちょうどあのトラークルの最後の詩の終行と同じように、問いかけている。
「この世界を覆う死の饗宴の中から、雨の夜空を焦がしているあの恐ろしい熱病のような業火の中から、そういうものの中からも、いつかは愛が生れ出てくるであろうか?」(同、七七六頁)
トーマス・マンの大部の論文『非政治的人間の考察』を例に挙げるまでもなく、第一次世界大戦はある意味において、その四半世紀後に再びヨーロッパ全土(さらには全地球)を破壊の坩堝に突き落した第二次大戦よりも、遥かに深刻な終末論的様相を帯びていたといえる。それは何よりも精神に対する強力な破壊力として、それまでの人間の営々たる精神の営みを無に帰さしめた。この破壊と暴力の嵐の中に、さらに人間の歴史を押し進める肯定的な力があることを見出すには、その力はまだ余りに未成熟だった。個人の運命はそれ故、そのまま人類の運命にまで極端に主観的な普遍化をなされ、歴史的諸潮流はその混沌とした外相のために正しく分析区別されることもなかった。
戦争の歴史的意味の代りに、その終末論的意味の方がこうした状況の中では一層深刻な不安を掻き立てたことは確かである。この時ほど神が人間に近づいたことは、おそらく人間の歴史の中でなかっただろう。だが同時にまた、この時ほど人間が神から遠のいた時代もなかった。つまり、絶望の闇が深まるにつれて、精神は一層激しく神を呼び求め、この闇を突き抜けようとするが、それは結局、地上の者としての人間と神とを隔てる深淵の深さを証明するにすぎないからである。
ゲオルク・トラークルの死の意味について語ることはむずかしい。否、そもそも人間の死の意味について語ること自体、途方もなく困難な仕事である。死そのものでなく、死の意味について語るということは、結局、かれの生の全体の意味を問わねばならないからである。人間は死によってでなく、死の意味によって、即ち死を通してかれがさらに表現しようと意図した内容によって、かれの生の全体的意味の決算を試る。極論するなら、この最終的な表現行為としての死に含まれる意味こそが、かれの存在の意味なのである。
いまはただ、この序を終えるにあたり、フィッカーの言葉を無反省的に引用しておくだけにする。
「かれ(トラークル)は運命に強いられ、迫り来る世界戦争の中で増幅されていった世界の狂気に、それを精査すべく、身を任せ、自分の生の固有の意味を、その意味に含まれているいっさいの疑しいものを含めて、見つめたのである。」
一
次の手紙はトラークルからわたしに届いたもので、検閲済みの野戦郵便葉書に、かれ自身によって「クラーカウ第十五衛戌病院第五病棟」と記載されていた。
敬愛する友へ
私は五日前からここ衛戌病院に、精神状態の検査を受けに来ています。健康状態はおそらくかなりの打撃を受けているのでしょう、しばしば言いようのない惨めな気分に陥ります。このような意気阻喪の日々が早く過ぎてくれれば良いのですが。あなたの奥さま、お子さまたちに宣しくお伝え下さい。どうか二言三言で結構です、電報にてお言葉を下さい。あなたからお便りいただければ、どんなにか嬉しく思います。心よりのご挨拶を
あなたの忠実なゲオルク・トラークル
レックによろしく。
この文面から戦場のトラークルのところには、友人からのただ一通の便りも届いていないことを知り、わたしはクラーカウに向った。十月二十四日土曜日、わたしは早朝にその地に入り、翌日の夕刻まで滞在した。町も衛戌病院収容事務局も慌しい動きでごった返していた。三方からのプルツェミュスルの包囲と北からの敵の圧迫が、脅威的な状態を生み出していたのである。
わたしが自分の用件を告げ、病気の友人を――できればすぐに!――自宅看護に移されるよう許可されたい、と余りにも民間人的な、それ故明らかに幾分素朴な希望を述べると、チェコ人の医師長は放心したような顔付きで、黙ったまま、わたしの希いを拒絶するかのように、ただ頭を振るだけだった。だが、その場に居合わせていたポーランド人の医局員が、トラークルの治療には自分が当っています、と言って、わたしを脇の方へ連れて行くと、かれはこの症例に強い関心を持っている旨を説明した。自分の希いを聞き届けてくれるにふさわしい相手を得たことを嬉しく思い、わたしはかれの専門的な興味や人間的な関心を喚起するようなことをあれこれと語った。特に、トラークルの場合、こうした抑欝状態は決して珍しいことではなく、相応の環境に置かれれば、往々にして急速に緩和するものであることを指摘した。それからさらに、わたしは、面会時間外ではあるが、いますぐ友人と話をさせてくれるよう許可を求めた。医師はこの点については諒解してくれた。
精神病棟の地階の廊下で、わたしは通りかかった看護人を止め、トラークルのことを尋ねた。かれはすぐ傍の黒いペンキ塗りの扉に近づき、覗穴を開けた。
「あの男のことかね」
――わたしは中を覗いた。
「……どうも――ええ、そうです」
トラークルは上着のボタンをだらしなく掛け、寝台の縁に腰かけて、煙草を喫っていた。落ち着いた様子でかれはいま、向いの男(わたしにはその男の姿は見えなかったが)と話をしているようだった。天井の高い小さな部屋は煙草の淡い煙で霞んで見えた。だが、頑丈な十字格子の嵌った高い窓から射しこむ早朝の溢ふれるばかりの陽光が、軽やかに揺らめく朝露のように、煙を黄金色に輝かせていた。突然、トラークルは煙草を傍に置き、ほとんど気づかないほど頭を動かすと、わたしの視線を迎えるかのように緊張した面持で、扉の方を見た。その時、すでにわたしの方も扉を開けていた。――そしていま、友は立ち上がり、大きく見開いた眼でわたしを見つめながら、物静かに近づいて来ると、一口も言わないでわたしを両腕に抱いた。
かれの態度には何ひとつ変ったところはなく、実に落ち着いて見えた。気分はどうですかと、わたしが尋ねると、かれは答えて言った。まあまあです。それにしてもここでこうしてお目にかかれるのは偶然です。もうこの病院を出て行くところだったのです。――そう言いながら、かれは夜具箱から一枚の野戦郵便葉書を取り出して、わたしに見せた。
「ごらん下さい、ここにあなたに宛てでそのことを知らせておいたのです」
だが、かれはその葉書(わたしはそれにざっと目を通すと、かれに返した)を投函しなかったのだった。最近、軽い偏頭腺炎に罹って、そのためにここにまだ暫くいなければならなかったものですから。でも、もう熱もなく、良くなりました。それなのに不可解でならないのは、この状況からわたしを解放しようという決定が、どうも医師たちの間でぜんぜん問題にもされていないようなのです。わたしの印象では、連中は何かと口実をつけてわたしを引き留めようとしているのです。
わたしはかれの疑念を拭い消そうとした。しかし、その時自分自身にも胸に迫って来るものがあった。手紙の検閲の折にトラークルの幾つかの詩をも眼にしていたという医師との話から、この症例を「天才と狂気」の問題のひとつと考えている、といったかれの言葉が念頭から離れなかった。それによってかれは、さらに継続的な注意と観察が命じられているのだ、と示唆しようとしているように見えた。
それにしても、トラークルの疑念がどの点に集中していたのか、わたしはその日の午後知ることとなった。薄雲のかかった素晴しい秋の日だった。空気はほとんど春のように穏かで優しかった。トラークルは戦場で体験した些かな、だがかれにとってはあまりに宿命的なことを物語った。感情を抑え、常に一瞬何ごとかを思い起こし、忘れえぬことを眼前に思い描こうとすることだけを気にかけているような話ぶりだった。[end]
グローデクの戦いの時だった。決戦直前ですでに前線にはその反動として恐慌状態が起っていた。かれの所属する衛生部隊が初めて投入された。町の大広場近くの一軒の納屋で、かれは医師の助けも得られずに、九〇名の重傷者の看護を引き受け、気力もなす術もなく、この苦しみにまる二日間耐えなければならなかった。いまでもまだ苦しむ者たちの坤吟や、この苦痛に終止符を打ってくれと希う声が耳の奥に残っているのです。突然、この悲惨な状況の中ではほとんど聞きとれないくらいでしたが、低い爆発音が起ったのです。膀胱を射たれたびとりの兵が、頭部に銃弾を討ちこんだのだった。そして不意に、血の滴る脳の破片が壁面に貼りついた。その時、かれはもうその場にいられなかった。でも外に出るたびに、恐しい別の光景がわたしに付き縫い、身体を強張らせたのです。混乱でごった返していた広場は、やがてまた、まるで掃き清められたように見えた。・そして、その広場に不気味なほど静かに木々が並び立っていた。その木々の一本一本に絞首刑にされた者がぶら下っていた。かれらは町の定住者と正当に認められていたルテニア人だった。かれらのひとりで、最後に絞首にされた者は、トラクルの聞いたかぎりではク・(それとも、かれもその場にいてそれを体験したのだろうか)、自分で首に針金を巻いたのだった。深くわたしはその光景を心に刻みつけました。人類の全苦悩、いまここでわたしはそれに触れたののだ!と。わたしは決しでこのことを忘れることはできないでしょう。それに退却もありまケん。というのは、錯乱の中へ退却することほど恐しいことはないのですから(注)。
(注)この事件の目撃者、薬学専攻者のラウスキー・コンロイは後年(一九五四年)、オーストリア薬学新聞の記念号で、このことに関して書いた。1わたしはトラークル一が驚愕のあまり目を見開いて、納屋の板壁に免れているのを見た。帽子がかれの手から滑り落ちた。かれはそれに気づかず、励ましの言葉にも身をかさないで言つだ。『わたしはどうすれば良いんだ。どうやって助けろと言うんだ。もう耐えられない』一わたしは制服から、その時あまりの絶望のためいまにもだめになってしまいそうなこの人物が、自分のかなり親しい戦友だということを知った。なんとか助けようと思い、わたしが自分の名前を告げると、かれも名前を喚くのだが、憐れなことに、かれはわたしの励ましにはほとんど注意を向けていないように思われた。わたしはさらに先へ行かなければならなかったので、かれとの約東に従って、できれば医師の援助をこちらへ寄こすつもりでいた。だが、残念ながら、それはうまくいかなかった。(編者注)
そしてある晩――と一トラークルはさらに語り続けた――どこかまだ退却の途中のことでした。戦友たちと一緒に夜食を取っていたとき、わたしは突然立ち上がると、もうこれ以上生きられない、どうか許して欲しい、死ぬより仕方がないんだ、と不安に狩られ釈明しながら、外へ飛び出したのです。すぐにかれの後から追いかけた戦友たちが、力も意志も意識も衰えたかれの手から拳銃を取り上げた。いま思うと残念なことです。わたしがいまこうしてこんなひどい状況にいるのは、この突発的な絶望のせいです。だってその卒倒からはすぐに回復して、それ以後興奮することもなく、わたしは通常の勤務に就くことができたのですから。その二週間後――リマノワで――かれはこのクラーカウ衛戌病院への転属命令を受けた。かれの推測では、それは薬剤師としての職務遂行のためではなかった。――もうご覧になって、あなたもお分りでしょう。ここではまるで何もすることはないのです。
そしてトラークルは不意に立ち止ると、両手を背中に回し、深いもの思いに沈んだ-不吉なことにいつもどうしてか被告服を思い出させる、かれの着た患者服には憐れにも人間の尊厳のひとつの姿が窺えた!。やがてかれは突然頭を上げると、不安な、問いかけるような眼で凝っとわたしを見つめた。
「どう思いますか。わたしはあの事件で戦争裁判にかけられ、処刑されるのではないか、と思うのです。臆病、おわかりでしょう。つまり敵に対する戦意喪失の現われ、というやつです。――わたしはそのために捉えられているにちがいありません。」
驚いて、わたしはかれのこんな妄想をなんとか説得して棄てさせようとした。
「いいえ、そんなことはありません。どうしてそんなふうに考えるのです。」――
「ああ、そうなんです」、とかれは自分の意見を譲らなかった。「いろいろ前例があって、そんな気がするのです。それ以外に-何故わたしはここに拘留されているのですか」
――ええ、そのことについては、とわたしは答えた。近いうちにきっとあなたをここから自由にし、療養のため家へ連れて帰ってあげられると確信しています。ですから、どうかご安心なさい、と。その間に陽はすでに沈んでいた。冷えて来たのでわたしたちは建物の入口の方へ向った。中へ入る前にかれはもう一度立ち止った。
「それでは――違うのですね。そんなことはない、とあなたは思われるのですね」――「そうですとも、友よ、そんなことはありません。一体何んていうことをあなたは考えるのです!」
振**妄に罹っているヴィンディシュグレーツ竜騎兵隊太尉がかれと部屋を共有していた。この男は、数日後にはスロバキアの資産家の父親に連れられて、療養休暇で帰省することになっていた。気むずかしいこの人物との戦友関係のために、狭い部屋が二倍にも重苦しかった。がしかし、トラークルはこの不幸な男に対して感動的な忍耐と寛容さを示して、それに耐えていた。眠りから眠りの合間に、上気嫌な時には全く馬鹿げていると思えるほどの情報伝達欲の発作と交互に、この男の怒りが爆発した。自分に従者がいないために、トラークルに付き添っていた従者が、かれのために何ひとつまともにできないからといって、きたない侮辱的な言葉を浴びせた。一度、わたしのいる時に、罵里言雑言を浴びたこの著者は、怒りを爆発させ、全身を震わせて、苦悶に大声を発し、トラークルを指差して叫んだ。
「あの人がわたしの主人だ、あなたなんかじゃない!」
これに対して、トラークルはひたすら自分を抑えて、怒り狂っている戦友に成した。
「お願いだきみ、なあ――あの可哀相な男のことは放っておいてくれないか。きみにも分るだろう、かれはできるだけのことはやってるんだ。」
その上、不安とか外の廊下の絶間ない往来、看護人の粗暴な態度、上階でときおり起る狂人たちの喧燥と叫喚、さらに迫り来る暗闇の中で慰めようもないものへと濃密化していく監房の印象といったものが、それに知った。そしてついに夜になると、たちまちにしてこの世の恭順な被造物たちが全て、無意味な暴力に曝されているということが忘れようのない印象へと高められる。蒼ざめて病気のような顔付きをしたトラークルの従者は、窓側の壁と鉄製寝台との間の一隅の、主人の枕辺で寝るために、床の一山の木毛の上にテント布を拡げた。これがわたしと文とめ最後の出会いがなされた状況だった。
次の日の午後、わたしは床に就いているかれのところへ行った。前日に比べ、かれは気持が塞ぎ、まだ感じられた落ち着きが表われているようにみえた。
「戦場で書いたものを聞いていただけますか」とやがてかれは尋ねた。「つまらないものですがしと付け加えた。
ヴィディシュグレーツ竜騎兵は、わたしがまたやって来たことに明らかにおもしろくなさそうだった。かれは欠伸をすると、退屈そうに寝台の中で壁の方を向いてしまった。トラークルは小声で、かれ独特の飾り気のない眩くような調子で、二篇の詩をわたしに朗読してくれた。嘆き『グローデク』である。かれの最後の詩となるこの『グローデク』の草稿は、生まれざる子らの運命を展望するその締括りの部分が、まだ(現在の草稿より 訳者注)幾分長く、あの突然の展望の短縮化――トラークルの視線が文字通りそこへ侵入して行って、世界から消え去ってしまったかにみえる――はなざれていなかった。わたしは感動していた。向いの眠っている男の痛々しいほどの大きな軒が、静寂をついて響いていたが、わたしは友の物悲しい沈黙に、まるで死んで干澗びた腕に抱かれるかのように、いつまでも包まれていた。
「ブレソナーに載せてくださいますか」、とかれはやっとのことで尋ねた。
「喜んで」、とわたしは答え、かれに礼を言った。
「いつごろ出版されるつもりですか」
「できれば新年にも、年鑑として……それもしかし、戦争がすぐ終るか、それともわたし自身入隊して、出ていかなければならなくなるかに掛っているのですが。」
「神よ御加護を」、と咳くように言うと、かれはぼんやり自分の前方を見つめ、黙った。それから、夜具箱の上に置いてあった一冊のレクラム文庫を取ると、わたしに手渡した。
「これをご存知ですか」
わたしは知らない、と言った。それはヨーパン・クリスティアン・ギュンターの詩集だった。
「わたしもかれのことは知りません」、とかれは言った。「ですが、かれは人々に知られるだけの価値はあります。いままさにドイツで知られるだけの。かれのことを心に留め、忘れないでおくだけの価値は……」とかれは一瞬思いをあぐらし、さらに続けた。
確かに――そう、こう言わざるを得ません――かれの詩行の多くは、ほとんど耐えがたい、正当とは言えない苦汁を帯びています……失礼!」
かれは、最後の数頁だけが切り開かれているその本をわたしの手から取って、頁を繰った。
「これはこれまでにドイツの詩人が書いた中で最も苦い詩行です――お聞き下さい。」
そうして、かれは読んだ。
わたしは恐じく不安でならない。西方から稲妻の閃きが走り、
北はすでにお前の上に迫っている、
お前が耕すのは、おそらくはただ異邦の客人らのためにすぎない、
それはわたしの希はぬこと。わたしのことを忘れるな。
お前はわたしを迫い払い、呪いの言葉を浴びせるがいい、
我、炎に立ち向うビーアスの如く滞まらん、
汝、運命の呼び声に従いて、いづこなりとも行くべし、と。
いまわたしはお前の元を去る、
お前からもはや何ひとつ享けようとは思わぬ、
たとえこの一口の空気さえも。
「祖国に寄す、という題です」、とトラークルは、暫くの休止の後に語った。――「これはその最終連です」――そして、かれは頭を振った。それから、まるでその詩行の苦汁を飲み下そうとでもするかのように、最後の三行を暗語した。その後で改めて本を取り上げた。
「しかし、最も美しい、最も重要なのは、いいですか、最後の詩『蹟いの思い』ですqギュンターが若くして、二十七才で死んだことは是非憶えておいて下さい」そしてかれは読み始めた。
神よ!すでにわたしの人生の春は
かくもひそやかに、人知れず、早々とどこへ過ぎて行ったのか
かれは静かな感動的な仕方で、その二十五連の詩を読んだ。感傷を殺したその単調な調子の中から、かれは次第に憂愁をかき立てながら、次の美しい詩連を強調して。
姿現わしたまえ、あなたの御心のままに原罪を呼びよせたまえ。
肉体、重々しい衣は千々に裂け、朽ち果てるがいい、
この腐敗が新しい光でそれを飾るものなら。
わたしはあらかじめ、歓び憧れの思いを抱いて
肉体を墓所の微睡に少しづつ慣れさせよう、
この微睡の中でなら、もはや空しい夢が肉体を苦しめることもない。
そして吐息を洩らし、弱い消えいるような調子で、さらに続けて、
おお、優しい臥所よ、至福の広野よ、
お前はわたしに楽園をまざまざと見せてくれる、
なぜか、わたしは深い感動に心を震わせている。
やがて最後に、
予期しない没落がこの肉体を突き落すなら、
あなたの胸に抱いて、わたしの苦悩の時を
縮めたまえ
自由な心を腕を拡げ、同情の思いで受けとめたまえ。
いまもまだわたしに怒りを抱く者、
その者の心に、わたしの棺に記された言葉が刻まれよ。
良き死こそは広々にして最良の生涯なり、と。
かれがそう語り終えたとき、かれは樵僻し、休息を必要としていた。かれは眼を閉じた。わたしはかれの寝台に腰かけていた。静かな時が流れて行った。かれの寝台の向いの病人は、胸の中に膨れあがって来た重苦しさに一眼覚め、寝たまま濁った眼でわたしの方を見た。外は陽が傾き、先ほどまで床に延びていて、徐々にその影を失っていった窓格子の影は、暗がりに掻き消されてしまったようだった。かすかな光が部屋に漂っていた。わたしは、どうしてよいか分からなかった。寝台の下にビールの壌が、中身の入っているのやら空のものやらが一列に並べてあった。わたしの足が思わずそれに当ったとき、かすかな音を立てて、ぶつかり合った。まるで世界は見棄てられてしまったように思えた。がすぐに、敢えてわたしは告白するが、これが永遠の別れになるかも知れない、という考えが心に浮んだ。友の姿にはこの世のものとは思えない何かが、強く否定しがたく現われていた。やがてかれが身体を動かし、もう何時頃なのか、自分は眠ってい。たのか、と尋ねたとき、わたしは気を取り直して、話題をとりとめのない事柄へ向けようとした。勿論、それがうまく行かないことはすぐにはっきりした。だが、そのときトラークルに偶然を装って、かれがまだいまも毒物を持っているのではないか、と尋ねる機会が生まれた。「もちろんそんなことはありません、薬剤師として、とんでもありません」、とかれはほとんど陽気なくらい気嫌よく頬笑んで答えた。「さもなければ、わたしはいまごろどうして生きていられるでしょう……どうか分って下さい、ここでは誰もそんなことはできないことははっきりしています――そうでなければ、わたしはうまくやれるのでしょうが。」
その直後、医師が戸口から頭を突込んで、「気分はどうです」と尋ねた。夕方の回診だった。かれの後を追ってわたしは廊下に出ると、トラークルの即時釈放と療養休暇の許可に対して配慮願いたい、といま一度かれに頼んだ。かれは急いでいたが、あっさりと、だが少なくとも本心から約束してくれた。わたしはこの朗報を持ってトラークルのところへ戻った。だが、かれは吐息を洩らし、自分の中へ引き籠ったきり、医師やかれらの言葉についてもう多くを知りたがらなかった。やがてかれらの従者が食事を取りに行ったとき――その間に暗くなっていた――わたしは、いよいよ友に別れを告げる時が来た、と思った。寝台に歩み寄り、心を落ち着けてから、帰途ウィーンでも、かれの退院をそこから働きかけてもらい、早くしてくれるように、でさるかぎりのことをするつもりだと約東した。そうなればまたインスブルックで、それも近々お会いできるでしょう。
「そう思われますか」、とかれは気のない、小さな声で言った。
「わたしは――そうなると期待してます」、と答え、一瞬とまどった。トラークルはしばらくわたしの手を握り、訪問の礼を述べると、友人たちによろしく伝えてくれ、と頼んだ。それから、眠りこむ前になおしばらく物思いつつ暗闇の中へ赴こうとする人のように、横になると、毛布を引き上げた。わたしが戸口のところで振り返ったときには、部屋はもうすっかり暗く、かれの顔を見分けることはほとんどできなかった。もう一度かれに頷きかけ、思わずまた二三歩近づいて
「さようなら、愛する女よ、またすぐに会いましょう」、とまるで夢の中でのことのように、わたしは言った。
トラークルは横になったまま身動きもせず、一言も答えなかった。わたしをただ凝っと見つめていた。いつまでもわたしを見送っていた……
わたしは決してあの眼差を忘れることはできないだろうo
二
インスブルックに戻ると――わたしはウィーンに戻週間近く滞在し、そこで必要な手続きを取った――、トラールから二通の手紙が届いていた。それらは同じ日に、つまりわたしが帰った翌日に書かれたものだった。
〔L・F宛〕クラーカウ、一九一四年一〇月二七日
敬愛する友へ
あなたに約束しました二篇の詩の写しを同封致しします。病院へお出いただいて以後、気分の方は倍もみじめなものです。最後に;日、わたしが死んだ時には、わたしの所有する金銭およびその他の品は全て、愛する妹グレーテに与えたい、というのがわたしの希いであり意志でもあります。愛する友に心からの抱擁を。
あなたの
ゲオルク・トラークル
〔この手紙に、トラークル最後の詩が二篇、鉛筆書きで添えられている。〕
嘆き
眠りと死。暗欝な鷲がむらがり
夜通しこの頭蓋の上で羽撃く
人間の金の姿も
永遠の凍る大波に呑まれてしまうと
脅かしつつ。おそろしい暗礁に砕け
紫の肉体が飛びちる。
暗い嘆きの声が
海原をおおい
おお 嵐の憂欝の妹よ
小舟が翻弄されて沈んでゆく
星空の下
夜の沈黙する顔に見まもられつつ。
グローデク
夕暮の秋の森がひびきわたる
死の砲火につつまれ。金の野や
青い湖をこえて太陽が沈みおちる。
ひときわ昏く落ちて夜がいだく
死んでゆく兵士を 惨い歎きを
洩らす砕かれた口を。
おお柳の茂る谷で
怒れる神が住む赤い雲が
流れた血を畷っている。月の冷気。
街々は黒い腐敗のなかにおちて
夜の金の枝と星のしたを
妹の影が黙す杜をとおってゆく
勇士らの霊と血にぬれた亡骸を弔いつつ。
秋の暗い笛がかすかに葦のなかでうたう。
おお 気位高いかなしみ。青銅の祭壇よ
大きい苦しみがいま精神の熱い炎をはぐくむ
生まれていない高の者らを。
〔L・F宛〕〈クラーカウ、一九一四、一〇、二七〉
敬愛する友へ
わたしの第一詩集の中の詩「人間の悲惨」の改稿、および詩「悪の夢」の第一連の修正稿を同封致します。
人間の悲愁
日の出まえに五時をうつ時計――
暗い戦懐が孤独な人びとを襲う。
たそがれの公園で枯れた樹々がざわめき
死人の顔が窓のあたりで動く。
おお 時も移るのを止めるようだ。
河べりで揺れうごく舟の拍子にあわせて
夜の幻が濁った両眼のまえでおどる。
波止場を風に巻かれて通ってゆく妹らの列。
あれはこうもりの叫び声であろうか。
庭で枢をこしらえる鎚の音もきこえる。
崩れた石垣のあいだに骸骨がちらつき
黒くあそこを狂人がよろめいてゆく。
秋の雲のなかで青い光線が凍りつく。
恋人らが眠りながら体をからみあわす。
星の光る天使らの翼によりかかった
高貴な人の白いこめかみに月桂の冠。
悪の夢
弔いの鐘の音は止んで
愛をいだく男が黒い部屋で眼覚め
窓にまたたく星たちに頬をよせる。
帆やマストやロープが河で光っている。
他の連は修正なし
いま一度、心よりの挨拶を――ティロール、あなた、そして全ての人々に。
あなたの
ゲオルク・トラークル
三
その二三日後!わたしが帰って来てから四、五日足らずしか経っていなかった――のことだった。午後、街からの帰り道で、郵便配達夫がわたしに一枚の葉書を手渡した。トテークルの手筆による、次のような内容のものだった。
敬愛する友へ
わたしは今日まで生の徴しを受け取っていませんので、わたしの野戦郵便葉書をあなたが受け取っていないものと思います。この地の衛戌病院に二週間いましたが、クラーカウを離れることになりました。どこへ行くことになるかまだ分かりません。新しい住所はできるだけ早くお知らせするつもりです。
心よりの挨拶を
あなたの忠実な
ゲオルク・トラークル
わたしはすでに一度読んだことがあるような気がした。そして突然、それはトラークルがわたしのクラーカウ訪間前に書いて、その地でわたしに見せてくれた例の葉書だ、ということを思い出した。いったいどういうつもりで、いまごろ送る気になったのか。不安に襲われて、わたしは葉書を裏返してみた。すると住所面に見慣れない筆跡で、読みづらい文字の添え書があった。
「トラークル氏はクラーカウ衛戌病院にて不慮の死(心臓麻痺?)を遂げられました。
私は氏の同室だった者です。」
その葉書はプラークで投函されていた。日付は一九一四年一一月九日の消印になっていた。
四
それから間もなく、わたしのところにまた、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインからの便りが届いた。それまで断っての希いでかれの名前をわたしは秘密にしておいたが、トラークルがまだインスブルックにいた時、例の若い芸術保護者で、わたしがすこし以前にリルケとかれにかなりの額の金を配分できたのは、かれのおかげである、と打ち明けたことがあった。ヴィトゲンショタインはその当時、ウィーン学派内にとどまらず、実証主義思想家のグループの間ではすでにその名前は知られ、評価されていた。戦争開始と同時にかれは志願入隊し、当時クラーカウ要塞砲兵隊での訓練を終えていた。クラーカウにいる間にわたしはヴィトゲンシュタインにも会いたいと思っていたが、残念ながらだめだった。求める人は、ヴィスワ河船「ゴブラーナ」勤務に就いていて、何週間か前から外へ出ていた。だが、その偵察航は間もなく終ることになっていた。そこでわたしは不在者に宛てて、かれの所属する司令部に、トラークルの容態が思わしくなく、当地到着後速かにかれの世話をお引き受け願いたい、と二、三行の伝言を残しておいた。ヴィトゲン・シュタインが帰還し、病院に赴いたときには、しかしトラークルはすでに死亡し、埋葬されていた。「たしかにかれのことは知りませんでしたが、わたしはショックを受けています」、との内容の第一報が間に合わなかったかれからわたし宛にあった。もっと詳しい事情を知らせていただきたい、との求めに対して、わたしは以下のような返事を受けとった。
一九一四・十一・一六
フォン・フィッカー様
九日のあなたのお葉書に対して心よりお礼中し上げます。私が哀なるトラークルの最期について知り得たことは、ただつぎの通りです。かれは、私の到着三日前に心臓麻痺で死亡しました。
ただひとつ重要なことがすでに言い尽されているこの報告に対して、さらにその上、諸々の事情について尋ねる気持には、私はなれませんでした。
十月三十日私はトラークルから面会を求める一通の葉書を受けとりました。私は折返し、数日後にはクラーカウに着くつもりですから、すぐにうかがいましょう、と返事しました。
願わくば良き御霊があなたを、そしてまた私をも見捨てることがなきように。
あなたの忠実な
ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン
たとえわたしを介して、ヴィトゲンシュタインのことを知っていたとしても、トラークルが自分自身でかれに宛てて、尚も訪問を求める手紙を出したということ、このことはわたしにとっては注目すべきことに思える。患者としてかれが受けていた強制的精神治療のために、かれらの憂欝及び、現下の非常事態における自分の運命に対する不確かさは限りなく高められたにちがいない。そのかれが新たな自殺の誘惑に屈服したくはないと希っていた、ということをこのことは証明している。たしかにクラーカウでわたしがかれと別れたときのかれの落胆は大きかった。しかしまた、運命に対するかれの恭順な態度は、明日かつ感動的である。かれはこの運命に強いられて、迫り来る世界戦争の状況の中で増幅されていった世界の狂気に、それを精査すべく、身を任せ自分の生の固有の意味を、その意味に含まれているいっさいの疑わしいものを含めて、見つめたのである。死が。すでにいかなる生の可能性よりもかれにとって近しいむのたらざるを得なかった瞬間に、友の援助が一体となって生み出す力に対し、それを心を開いて迎えようとするこのかれの信頼感、この信頼感ほど感動的に、かれがこうした袋小路の状況の中で自己否定と自己保存というふたつの衝動の究極的なバランスを保つために義務づけられていると信じた配慮を証明しうるものは、ほかになかった。
悲劇的な実存的否定としてはっきりと現われているような生の運命の非運に対して、なおも不壊なる確信という希望の光を抱いて立ち向っていくことには、人はほとんど尻ごみするものである。なぜなら、トラークルが曝されていた人間の悲惨という奈落がここで思いがけずかれ自身を通して体験する光明というものは、軍隊病院の精神病棟でのかれの没落の暗闇になおも、死のアウラとしてびとつの明白な使命を、かれの生への意志がいま尽きようとしている際に、授けているように思えるからである。だがしかし、あの物悲しい状況の中での、果でもない陰欝なかれの死とかれとの別離のことを思う度に、光輝く雲のようにひとつの思い出がわたしの前に湧き上って来る。一九一四年五月の、あの急速に傾いて行った美しい春の夕暮のことだっ。た。トラークルとわたしは、ガルダ湖畔の町トルボーレを遥かに下方に臨む簡素なレストランの前庭で、ワインとパンを傍に、向い合っていた。もう遅い時間で、黙ったまま。かれはなだらかに傾斜するオリーブの斜面に目を遣って(何か物思いに耽っているようなかれの心には申し分のない眺めだった。)、わたしは南の方の青く夕闇につつまれていく湖を見渡していた。それ故、その状況はなるほど」回的なものではあった。がしかし、眠りにつこうとする自然の大なる静寂に包まれて、ともかくほとんど聖書的な気分にさせるむうな風景が穏かに昏れていくなかで、かれがいつまでも飽くことなく聞き入っていた孤独な鳥の喘ぎ声に呪縛されて、不思議な霊感がかれを襲って来ることが、あらかじめ予定されているような光景だった。この霊感は、後にわたしに捧げられた詩(「捕われたつぐみの歌」を指す 訳者注)の九詩行全ての中に汲みつくされ、結晶化されることとなる。この「捕われたつぐみの歌」を、夕暮と没落の中でのこの誘いの声を、沈黙の休止の中でもなお、「緑の枝陰の息吹き」となって詩人に近づいて来るのを、トラークルは当時自分自身の中から聞えて来るもののように、聞いていたにちがいない。そして酔い痴れて飛び上がろうと羽撃く夜の翼のかなたに――つまり、いわば深まる静寂の余音の中になおも――「金色の歩みがオリーブの樹の下に途絶える」のをかれは聞いていたにちがいない。全ての見棄てられた被造物らの生において、明暗を分ける不安な時のこうした幻覚が、高く掲げられた十字架(イエス・キリストの受難 訳者注)と結びつき「かすかに血を流す謙遜」、「花咲く茨からゆっくりと滴る露」を目の当りにして消失しながらも、すぐにまた、「憐欄の輝く腕が崩れていく心を抱く」という突然の苦痛に満ちた知覚の中に現われだとするなら、このことは、神に開かれた知力による真理といかなる関わりも持たない空想への没頭を意味するのではなく、全く逆である。即ちそれは、その瞬間へと埋没して行った現実からの強烈な光の侵入であり、ゲオルク・トラークルのような驚くべき予知能力と、「ああ神様一切は解けませぬ。恐れれおののいて跪くほかありませぬ、」というあの詩人の別の体験を、かれの圧倒的な幻覚との関わりにおいていつまでも記憶に留めているような天与の分別とを備えた悲哀の精神にのみ、この光は授けられ得たのである。
(了)
付記
(一)
出に用いたテキストは、ハンス・スクレーナー編『ゲオルク・トラークルの想い出』(ザルツブルク、オットー・ミュラー社刊、増補第三版)所収の『別離』である。本文中の草分けの番号、改行は訳者の判断である程度自由に行った。
(二)
訳文中のトラークルの詩は、平井俊夫訳『トラークル詩集』(筑摩書房刊)を用いた。
(三)
「訳者序」に於ける事実的事項の叙述には、オットー・バージル著『トラークル伝』(口ーヴオルト社刊)を参照した。
(四)
本来付すべき人物、地名等の注はいっさい省いた。
(五)
原文中、接続法と直説法とが混合している個所、前者を直接話法で訳出したため、文章表現上あるいは幾つかの混乱を招来することになったかも知れない。
|